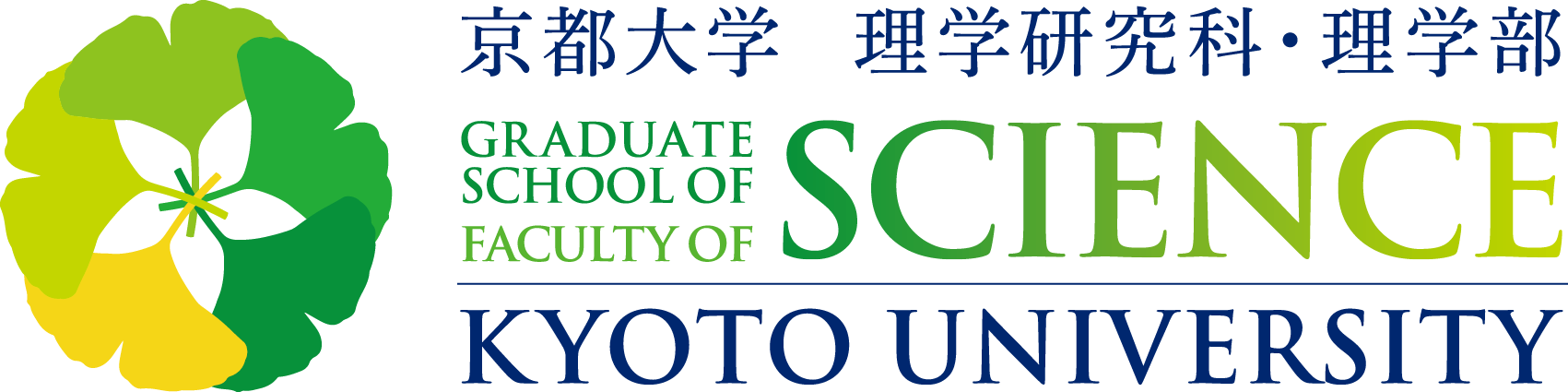国立天文台科学研究部 教授 生駒大洋
.jpeg)
太陽系外惑星の研究分野は、2010年代に本格化した宇宙望遠鏡による大規模な惑星探索によって、新たな時代を迎えたといえます。我々の知る多様な惑星および惑星系は量的にも質的にも増大し、いわゆるホットジュピターからスーパーアースへと、また、太陽型星を回る惑星から低温の赤色矮星を回る惑星へと、研究領域が急速に拡大してきました。さらに、惑星の「全体」の特徴に加えて、大気や表層環境という我々の存在と密接に関係する「部分」の情報が観測的に得られつつあります。こうした進展の中で、「第二の地球」を科学的に求める動きが本格化しようとしています。太陽系および原始地球大気の起源論を世界に先駆けて体系化した「京都モデル」を礎として、惑星系の多様性とその成因に関する理解は大きく進展してきました。本講演では、系外惑星に関する観測および理論の近年の発展を概観し、第二の地球の存在に関する現状の考え方についてお話しさせていただきました。
「第二の地球」に対して学術的な定義はありませんが、系外惑星研究分野では、海や湖など地表に液体の水が広く存在することが可能で、長期間安定的に温暖な気候が維持されうる惑星のことをいいます。最も重要な要素の一つが中心星からの距離です。中心星に近すぎると海は蒸発し、遠すぎると凍ってしまいます。つまり、中心星から適度な距離にあることが必要です。このような領域を「ハビタブルゾーン」と呼びます。太陽系では、我々の住む地球だけがハビタブルゾーンに位置しています。一方、全て恒星のまわりでハビタブルゾーンは存在します。銀河系には数千億の恒星があるので、第二の地球も数千億存在するかというと、そうではないでしょう。そこにどのような惑星が存在するかが問題です。
第二の地球の存在が科学的に議論されはじめたのは、それほど昔のことではありません。それは今から二十数年前、1995年に系外惑星が発見されてからです。その発見の功績によってミシェル・マイヨール博士は2015年に京都賞を、2019年には(ディディエ・ケロー博士とともに)ノーベル物理学賞を受賞されました。系外惑星が存在すること自体は必ずしも研究者に驚きを与えたわけではありません。衝撃的だったのは、発見された惑星系が太陽系とあまりにも異なっていたことでした。
太陽系の成り立ちに関する理解の大枠は、系外惑星発見の10年前(1985年)に林忠四郎博士の率いる京都大学理学部の研究グループが発表した「京都モデル」によって確立しました。京都モデルによれば、現在の太陽系の特徴はかなり自然に形成されるというものでした。しかし、初めて発見された系外惑星は、中心星のごく近傍に存在する、木星のような巨大惑星でした。この惑星系は太陽系とは似ても似つかないものであり、当時の研究者を驚かせました。それ以降、現在までに5000個もの系外惑星が発見されていますが、どの惑星系も太陽系とは大きく異なる構造を持っています。
それ以降、京都モデルの拡張または修正が続けられてきました。特に重要なプロセスは惑星の大移動です。京都モデルは、惑星は現在の位置で材料物質を集めて成長することを前提としていました。しかし、中心星から様々な位置に存在する系外惑星の発見から、惑星は現在の位置で生まれたのではなく、形成期に大移動したことを受け入れざるを得ません。実際、コンピュータ・シミュレーションを用いた近年の研究は、惑星が中心星に向けて落下することを証明しています。また、京都モデルでは惑星の成長のみを考慮していましたが、中心星からの強力な紫外線の照射によって、惑星が大幅に質量を失うこともあることが分かってきました。
このように、我々が当たり前と思っていたことが実は当たり前ではないことに気付かされました。例えば、地球の海水の量にも意味があるのです。最近の理論では、地球は適度な量の海を持つからこそ温暖な気候を保持できることがわかっています。実は、上述の太陽系形成理論とは別に、京都グループは地球原始大気形成理論も提案しています。それは、地球内部の成層構造の成り立ちを説明するもので、彼らは原始地球にマグマオーシャンが形成される条件として大気の毛布効果を導入したのです。残念ながら、その原始大気説は、地質学的証拠と合わないため、地球大気の起源としては受け入れられていません。しかし近年、岩石と鉄だけでは説明できないくらい膨らんだ惑星(低密度スーパーアース)が多数発見されています。京都グループの予言した原始大気は太陽系外にあるのです。そして、温暖な気候のための適量の海水を持つ惑星は、地球の海の獲得理論を応用すると殆ど形成されません。しかし、最近我々のグループで、京都グループが考えた原始大気に立ち戻り、マグマオーシャンと大気の相互作用を考慮すると、第二の地球というべき海惑星が数パーセントの確率で発生することが予測されました。
以上はあくまでも理論予測です。これらは観測によって検証されるべきでしょう。系外惑星研究分野では2020年代に多くの宇宙望遠鏡ミッションが予定されています。それらのほとんどに日本人研究者が参加しています。そして、2030年代の30メートル地上望遠鏡(TMT)へとつながるロードマップが描かれています。次の10年で、第二の地球の存在に関する我々の理解が大幅に進むと期待できます。系外惑星研究分野の今後の進展に関心を持っていただけると幸いです。